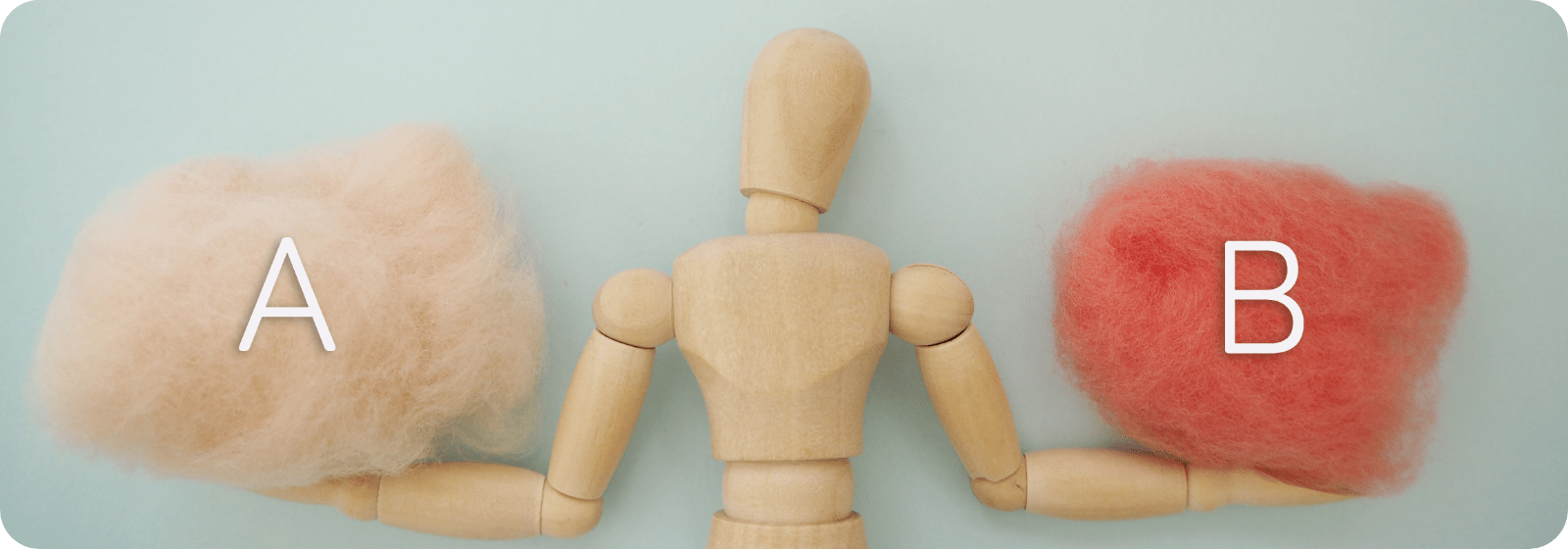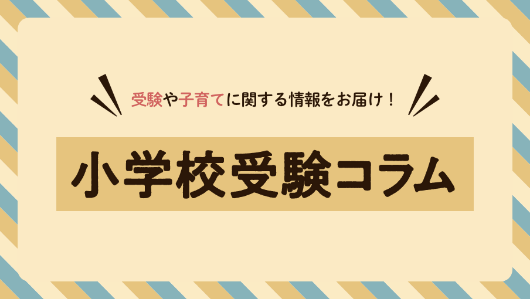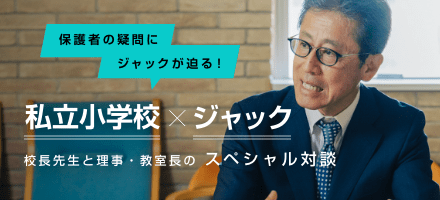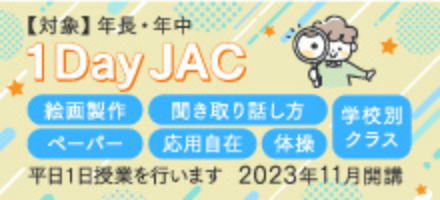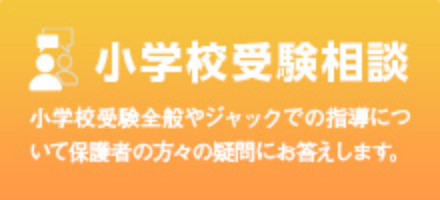小学校受験は、中学受験とは異なり「難関校を目指せば他校も受かる」という単純な構図ではありません。学校ごとの試験内容や出題意図を理解し、戦略的に準備を進めることが合格への近道です。本記事では、学校別の傾向分析から家庭学習の進め方、現実的な受験対策の組み立て方まで、合格率を高めるための具体的なアプローチを紹介します。
目次
難関校対策だけでは合格できない!小学校受験の落とし穴
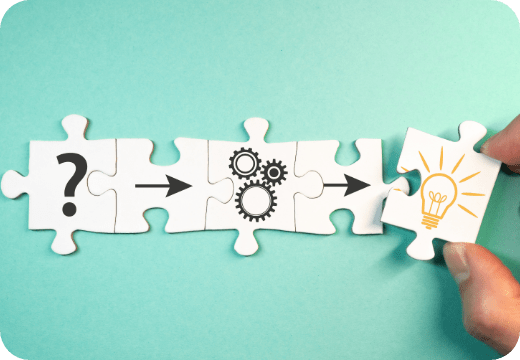
難易度の高い学校に向けて準備をしていると、それよりも低い学校はすべて受験ができて、そして合格率が高くなるというのが一般的な入試の考え方です。
しかし、小学校受験はそうはいきません。最も大きな特色は、入試問題、いわゆる入試科目が学校によって違うわけです。
小学校受験では学校別の合格対策が必須
例えば、慶應義塾幼稚舎の入試は絵画製作と体操になります。暁星小学校は1次がペーパーで、2次が体操と面接があります。このように試験内容もこれだけ違うと、幼稚舎に合格したからといって暁星小学校に合格するとは限らないということです。
また、一言でペーパーテストと言っても、基本的な問題を出題してどこまでできるかという正解率を求める学校もあれば、初めての問題に推理・思考を凝らした少し難しい問題を出して、地頭の良さを見るようなペーパーテストをする学校もあります。
それだけに、各学校の試験に応じた小学校受験の準備を進めていくことが合格への近道になります。
学校別に問題を調査・分析する小学校受験合格対策「学校研究会」
ジャックでは、それぞれの学校がどんな問題を出したのかを調査・分析して、「なぜその問題を出題したのか」ということを深く掘り下げることにより、学校側が求めているお子様像、そして合格するための家庭学習の仕方、またできれば次年度の予想問題などを解析する「学校研究会」というものを行っています。
大事なことは「何が出たか」というよりも「なぜその問題が出たのか」ということをよりよく知るということです。
合格に導くための現実的な小学校受験対策の計画
当教室では小学校受験の入試対策に関する研究を元に、学校別の授業というものを開講しています。年中までは志望校を意識せず、授業の復習、そして家庭学習の習慣化に集中する一方で、年長になると、進級と共に学校別の授業を少しずつ始めていきます。そして、4月頃からは学校別モードにスイッチを完全に切り替えて、小学校受験の準備を進めていくことで合格率を上げます。
例えば、小学校受験を4校受ける人が受験する学校すべての学校別授業を受けるというのは難しいことです。そのため、普通は時間的なものを考えれば、志望校の第1希望もしくは第2希望の学校別授業で対策をし、そして総合クラスでどの学校にも対応できる力をつけながら、志望校合格に向けて準備を進めていくというのが現実的な小学校受験の形になります。