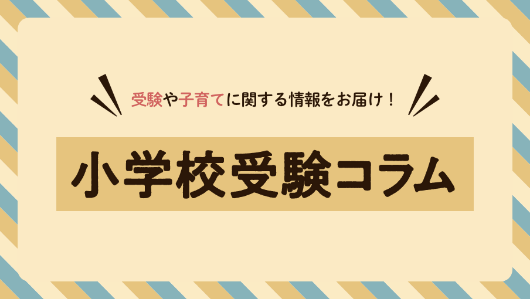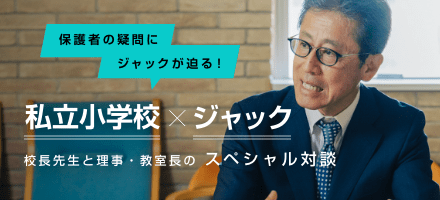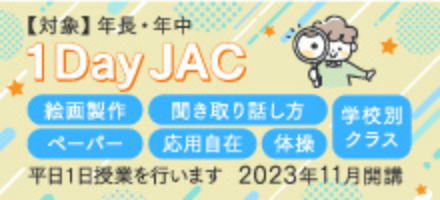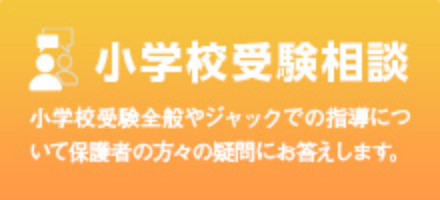小学校受験の相談では、志望校選びや学習方法、初めての問題への対応など、多岐にわたる質問が寄せられます。本記事では、相談内容の具体例や、より効果的な面談を受けるための質問の仕方、家庭学習の工夫について詳しく解説します。受験準備を始めたばかりの方や、これから始めようと考えている方に役立つヒントが満載です。
目次
小学校受験の相談で合格へ近づくためのヒントをもらおう
会員の方には「面談」を行っておりますが、一般の方には「受験相談」という形で面談を実施しています。

すでに受験準備を始めている方もいれば、受験するか迷っている方もいます。さまざまな方が受験相談を受けていて、相談内容も多岐にわたります。たとえば、「2校から3校を併願する場合の注意点はどういうことに注意したほうが良いか」「学校別クラスはどのように取ったら良いか」「保育園に通っている場合に家庭学習の時間を捻出するためにはどのように学習したら良いか」「絵を描きたがらない場合にどのように教えたら良いか」「子どもの能力を伸ばしきれていないと感じる」「問題の意味が分からないことがある」「初めての問題に弱い」「小学校受験の準備はいつからはじめたら間に合いますか」「小学校受験対策は今からでも間に合いますか」といった内容など、様々なご質問をお受けしています。
中でも最後にある受験に関する時期的な質問は一言でお答えするのが難しいです。
なぜなら、お子様の習熟度や志望校が違うからです。月齢や環境の違い、幼稚園か保育園かといったそれぞれに考えなければいけないことが違うため、質問に対する答えはよくお話をお聞きしたうえでお答えしていきます。
質問の仕方でアドバイスも変わる。小学校受験合格に繫がる面談に
保護者の方が質問される際、「プロなのだから、必ず正しいことを話してくれるだろう」と思って質問されるのですが、現実は必ずしも正しいことを言ってくれるかどうかは分からないことがあります。
間違ったことをお伝えするということではありませんが、すべての方に同じアドバイスをする先生には、多少注意が必要だと思います。つまり、間違ってはいないけれども、もっと良いアドバイスが存在します。
例えば、「初めてのペーパーや問題の意味が分からない」という質問に対して、「初めての問題に弱いのですね。たくさんの入試問題集を買って、初めての問題をいっぱいやりましょう。それをこなしていくしかありません。」と言われるかもしれません。もちろん、それもひとつの答えではありますが、それだけで保護者の方が納得できるでしょうか。
小学校受験合格に向けて試験本番で力を発揮するための家庭学習のアドバイス
私はそのような時に、保護者の方にこう尋ねることがあります。「お母様はお子様にペーパーをさせる時に、教えてからやらせていますか? それとも、やらせてから教えていますか?」と質問します。例えば、一枚のペーパーに果実が描かれています。
「この子はパイナップルとリンゴ、この子はミカンとパイナップル、この子はパイナップルとパイナップル、この子はバナナとパイナップル。それぞれ袋詰めをした時に、一番多く袋詰めできるのはどの子ですか。丸をつけてください。」という問題です。
このような問題の時に、まずやり方を教えずにお子様にやらせてみます。そうすると、「うーん、この子はパイナップルとリンゴだから1袋しかできないな。これは2袋できそう。これは…1, 2, 3, 4, 5, 6、6袋できる。これは1, 2, 3、3袋だからこの子が一番多い」というやり方をするかもしれません。もしくは、問題の意味が分からない子もいるでしょうし、問題の意味が分かって線を引きながら答えを導いていく子もいるでしょう。
このように、とりあえず1回やらせてみる。そしてやらせた後に、「今みたいに線を引くやり方もあるけど、でも実はそこまでやらなくてもいいんだよ。例えば、この子はどんなにパイナップルがいっぱいあっても、リンゴが1個しかないから1袋しかできないよね? ミカンが2個だから2袋だね。じゃあこの子は何袋できると思う?」「3袋。」「どうして分かったの?」「バナナが3本あるから」「そうだね。パイナップルがいくつあるか分からなくても、3袋より多くできることは分かるよね。だからこの子が一番多いということが線を引かなくても分かるんだよ」と教えてからやれば、そのやり方でやるかもしれません。
しかし、問題はたくさん出題されます。実際の試験のときには、問題の意味が分からない、問題の意味が分かってもその子が閃いた時に思いついた方法でやっていくしかありません。その思いついた方法が多少時間かかるやり方かもしれませんが、その方法で対処しなければなりません。
常に早く正確にできるやり方を教えてできる子に仕上げても、試験当日に今までやったことがない問題に出くわした時にその子は対処できるのでしょうか。
つまり、すべての問題において「まずはやらせてみる」、できたらそのまま続ければ良いし、できなくてもできないなりにやってみる。そして一問でも良いからやらせてみる。そのうえで「教える」、理解しているか確認するために「もう一度やらせてみる」、このような順番が大切です。
常に「教えてからやらせる」というやり方をしていると、初めての問題に弱くなりがちなので家庭学習のやり方を少し変えてみませんか? これもひとつの小学校受験における面談の形です。
小学校受験の面談を充実させるためには質問力が鍵
充実した面談を受けるためには、保護者の方も質問をする際に、できるだけ具体的に聞いていただけると良いと思います。
たとえば、「うちの子は平均点くらいは取れるけれども、それ以上がなかなか取れません。どうしたらいいでしょうか?」というご質問に対して、これだけではお子様に寄り添って答えるのが難しいです。
プロであれば例えば「平均点を70点と仮定して、10点のプリントが10枚あって100点満点の中で、70点取れているとします。では、その70点の内訳はどうなっていますか?」と質問するはずです。
例えば、どのプリントでも少しずつ間違えている、もしくはどのプリントも時間切れで全部はできずに7点のプリントが10枚集まっての70点なのか。それとも、7枚か8枚は満点が取れているけれども、残りの2、3枚で問題の意味が分からなかったり、何かの理由で丸々落としているのか。どのような形で70点になっているかによって、アドバイスの内容も当然変わってきます。
そのため、より良いアドバイスをするためには、こちらから質問して引き出し、それをもとに答えていくという面談の形が理想です。
できれば保護者の方からも、良い面談をするためにより具体的に質問をしていただくと、「この面談を受けて良かったな」と思えるような中身の濃い受験相談になるのです。
お子様にとって最初で最後の小学校受験です。志望校合格に向けて後悔のないよう、当教室の面談や受験相談をぜひご活用ください。