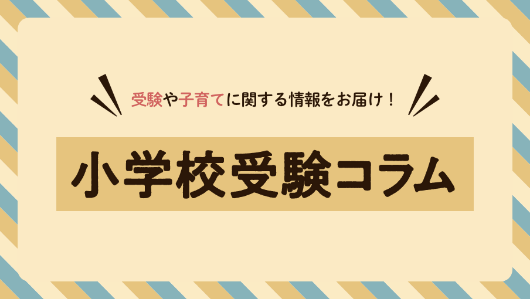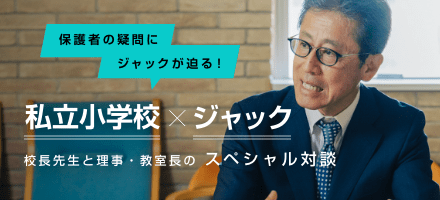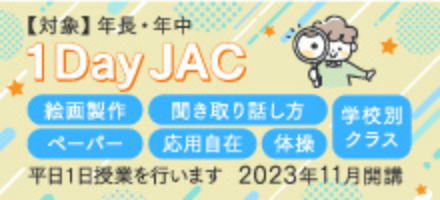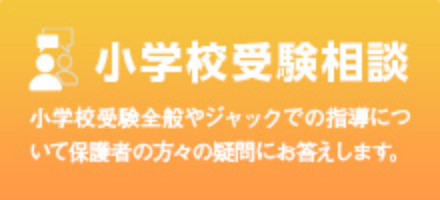受験では「正解する力」だけでなく、「答えを書こうとする姿勢」も重要です。幼児は確信が持てないと空欄にしがちですが、小学生は「とりあえず書く」ことを学びます。これは「間違えてもいいから書く」という経験を重ねた結果です。本記事では、試験当日に向けて、子どもの思考力と積極性を引き出す声かけのポイントをお伝えします。
目次
小学生受験と中学校受験の答案のちがい

幼児と小学生の答案には大きな違いがあります。迷ったときに書かないのが幼児で、間違えてもとりあえず記入しようとするのが小学生です。この違いが生じる理由として、小学生は3年生や4年生頃に「確率」や「確からしさ」を学びます。
例えば、幼児の問題には選択式の問題も多くありますが、小学生はどこかに記入すれば当たる可能性があることを理解しているため、間違えても構わずに記入します。しかし、幼児は確率の勉強をしていないため、自信のないものは書かない、記入しないという傾向があります。
小学校受験対策としては「空欄」を避ける
特に年長児の多くは、確率を知らないだけでなく、間違えるくらいなら書かないほうが良いと考えることが多いようです。例えば、問題が分からなかったときに「答えが分からなかったの?」と聞くと、「うん、でもこれが正しいと思ったんだけど…」という返事が返ってくることがあります。それでも記入しなかったのは、やはり自信がなかったからでしょう。しかし、実際には正解していたことが多いにもかかわらず、記入しないのです。
幼児にとって一番良い結果は「正解」、次に良いのは「空欄」、一番悪いのは「間違えること」だと考えています。この順序をまず書き換える必要があります。正解が一番良く、その次が間違い、そして書かないことが一番悪いという順番です。このようにしないと、「間違えたくない」という気持ちが強い子どもは、どうしても書かなくなり、記入に時間がかかるようになります。幼児にとって空欄は丸ではないけどバツでもないと考えているのかもしれません。
正解が多い子が小学校受験の志望校・志望園に合格する
最近、ある母親が子どもに「間違えたら落ちるわよ」と言ったところ、その言葉を素直に受け取り、答えを書くのに慎重になりすぎ、時間がかかるようになったと反省していました。このような素直な子どもほど、言葉に敏感で、慎重になってしまうことがあります。特に言葉かけには注意が必要です。「間違えたら落ちる」という言葉は、回答が遅くなる原因になりますが、それは正確ではありません。間違えた子どもでも合格することはありますし、正確に言えば、間違いが少ない子が合格するのです。
「正解が多い子が合格する」と伝えることで、子どもが積極的に答えを書くようになるでしょう。「約束を破らない人は、最初から約束をしない人」という言葉を聞いたことがありますが、同様に「間違いをしない人は、答えを書かない人」にならないようにしてほしいと思います。
小学校受験の入試対策において不正解の過度な指摘は厳禁
一般的に、親は正解を褒めるよりも、不正解に対して多くの時間をかけてしまいます。「なんでこんなことが分からないの?」「どうしてこんなつまらない間違いをするの?」といった言葉がけが多くなるのです。しかし、空欄の場合は少し勝手が違います。分かっているかどうかが分からないため、「もっと早くやりなさい」や「間違ってもいいから必ず答えを書きなさい」しか言えませんが、実際に間違えると厳しく叱られることが多いのです。これを理解している子どもは、答えを書くことに慎重になり、迷ったときには書かずに済んでほっとすることがあります。
小学校受験の試験当日のことを考えて言葉かけをする
試験当日に「間違えたくない」と強く思うあまり、回答に時間がかかり、空欄が多くなってしまったら、親としては悔やんでも悔やみきれないでしょう。また、面接でも同様のことが言えます。普段の模擬面接では、保護者がいないため、自分の考えを自由に話せますが、実際の入試の場では、保護者が同席するため、普段通りに話すことが難しくなり、慎重になりすぎて黙ってしまうケースが増えるのです。
保護者は常に入試当日のことを考え、どのような言葉かけをすれば、入試の時に子どもが気持ちよく書けるのか、話せるのかを考えることが大切です。特に年長の夏、これからはその点に注意して子どもに接していくことが重要です。
「3人に1人の保護者」とは、覚悟を持って子どもをサポートする親のことを指します。子どもが失敗したり、思い通りにいかなくても、ポジティブな言葉をかけ続けることで、子どもの可能性を広げることができます。日々の取り組みが積み重なり、結果的に子どもの成績や成長に結びつくのです。
小学校受験を控える保護者の皆さんに、本記事が少しでも役立てば幸いです。