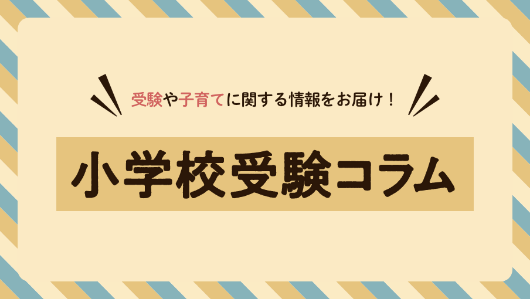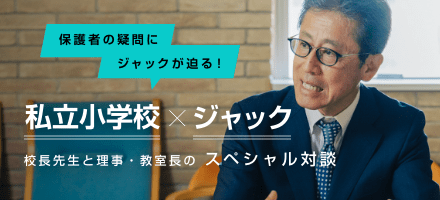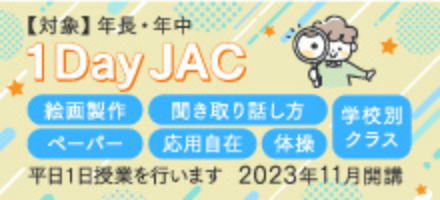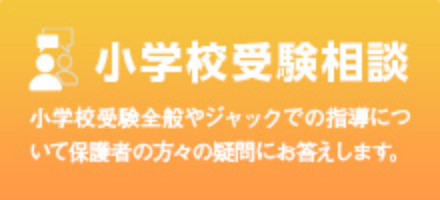子どもは生まれながらにしてポジティブな存在です。しかし、日常の中で大人の言葉や態度によって、そのポジティブさが失われてしまうこともあります。本記事では、子どもの自信を育むために保護者が心がけるべき言葉の選び方や、小学校受験を控えた家庭での接し方について解説します。余計な一言を省き、子どもの持つ力を最大限引き出すためのヒントをお伝えします。未来に向かって輝く子どもたちを、一緒に応援しませんか?
目次
子どもは生まれたときからポジティブ

赤ちゃんは生まれた時、みんな「王様気分」でスタートします。例えば、泣けばミルクや離乳食が与えられます。「気持ち悪いな」と思って泣けば、うんちやおしっこをしたことを親が察しておむつを替えてくれます。
ハイハイを始めれば、周りの大人たちはニコニコしながら手を叩いて喜びます。捕まり立ちや、頑張って歩こうとする姿も微笑ましく見守ります。もし、歩こうとして倒れても、「ああ、前はできたのに」とため息をつく親はいません。
だからこそ、赤ちゃんは何度も繰り返し挑戦し、やがてハイハイや捕まり立ちができるようになります。失敗しても「私には無理かもしれない」とネガティブに考える赤ちゃんは見たことがありません。みんな、生まれた時はポジティブそのものなのです。
小学校受験を目指す幼児もポジティブからスタート
小学校受験を目指す園児たちも、ポジティブな気持ちからスタートします。「将来の夢は何ですか?」と尋ねると、「サッカーのワールドカップに出たい」「宇宙飛行士になりたい」「お医者さんや警察官になりたい」など、自分の好きなことを堂々と語ります。子どもたちは、自分が「なりたい」と思ったものになれると信じているのです。
小さいうちは、こうした夢を聞いた大人も「頑張れ!」と声をかけ、応援する姿勢を見せます。しかし、中学や高校になると、「そんな簡単に夢が叶うわけじゃない」と現実を突きつけることが増えていきます。そして、その大人の多くが、実は親なのです。
小学校受験における家庭学習の大切さ
小学校受験では、合否の鍵を握るのは家庭学習です。しかし、家庭で問題を解いていて子どもがうまくできないと、つい「本当に考えているの?」「聞いてないからでしょ」「やる気がないからだよ」と言ってしまうことはありませんか?こうした言葉が繰り返されると、子どもに「勉強が嫌い」「自分はできない」「やる気がない」といったネガティブな印象を刷り込む結果になります。
ポジティブな子どもでも、こうした言葉を聞き続けるとネガティブな気持ちに変わってしまうのです。
受験合格の秘訣は保護者がかける言葉にある
同じ言葉でも、大人と子どもでは受け取り方が違います。例えば、大人が久しぶりに会った友人に「ちっとも変わってないね」と言われると、「若い頃と変わらない」とポジティブな意味で受け取ります。しかし、子どもに「ちっとも変わっていない」と言うと、「成長していない」「伸びていない」と感じ、悲しい気持ちになります。
さらに、「前よりできなくなった」「前より遅くなった」と言われると、それまでの努力が否定されたように感じ、自信を失ってしまいます。
小学校受験対策では肯定的に伝える工夫が重要
たとえ親が期待する基準に達していなくても、「前よりできるようになったね」「前より挨拶が上手になったね」といったように、「前よりも◯◯」という形で肯定的に伝えることが大切です。このように褒めることで、子どもの自信を育むことができます。
逆に、「前より覚えが悪くなったね」「前より体力が落ちたね」など、大人でもショックを受ける言葉は避けるべきです。
余計な一言を言わないことが子どもの自信を育む
自信をつけるために褒めることは大切ですが、私は「余計な一言を言わないだけで十分」と考えています。なぜなら、子どもたちはもともとポジティブな心を持っているからです。