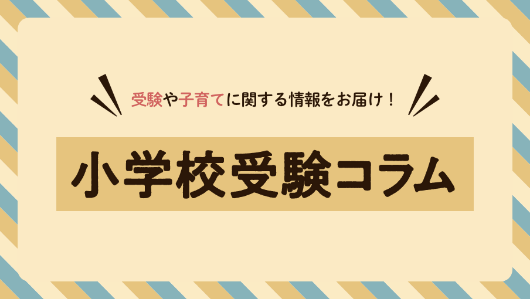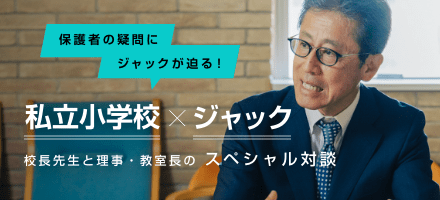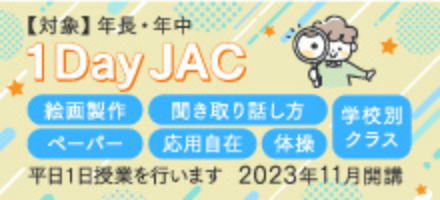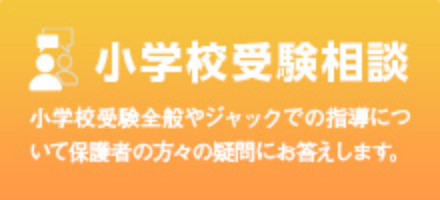小学校受験でよく耳にする「早生まれは不利」という話。本当にそうなのでしょうか?保護者が抱える不安に対し、専門家の視点から月齢考慮の実態や各学校の対応方法を解説します。また、低月齢のお子様が有利に受験を進めるための具体的なアドバイスも紹介。諦めるのではなく、楽しみながら学びを広げるヒントが詰まった内容です。早生まれだからこそできる工夫を知り、自信を持って受験準備に取り組みましょう。
目次
小学校受験における不安と疑問はジャックへ相談
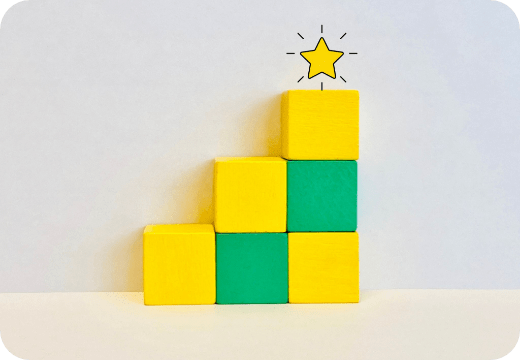
小学校受験は分からないことや不安に感じることが多いかもしれません。それはなぜかというと、保護者の方の中には中学受験を経験している方は多くても、小学校受験を経験している方は非常に少ないからです。小学校側から具体的な入試内容や合格基準について発表されることもほとんどなく、特に伝統校ではその傾向が顕著です。
また、周囲の小学校受験経験者からアドバイスを受けることもあるでしょう。しかし、その内容は人によって異なります。例えば、「早くから準備したほうがいい」という方もいれば、「1年間で間に合った」という方もいるでしょう。それは、受験する学校や受験者の習熟度、集中力が異なるため、正解が一つではないからです。疑問に思ったことはジャックに聞いてください。
小学校受験で月齢を考慮する学校とは
先日、ある保護者から「早生まれは小学校受験で不利ですか?」という質問を受けました。
結論から言うと、不利になる学校と不利にならない学校があります。つまり、月齢を考慮する学校としない学校が存在するということです。
月齢を考慮する方法は大きく3つに分けられます。
1.問題自体を月齢に合わせる方法
月齢に合わせて、難易度の違う問題を出す方法です。1月2月3月の早生まれのお子様は低月齢であっても、問題自体が違うため、不利にならない優しい問題を出すという方法です。
2.同じ問題であっても合格ラインを月齢に応じて変える方法
古い言葉で言うと、低月齢のお子様には少し下駄を履かせるということです。
3.全ての生まれ月からバランスよく合格者を選ぶ方法
月齢ごとの勝負になるため、1年間見たときに全ての月齢、誕生日月からバランスよく生徒を取ることで、その月齢の中の勝負になります。低月齢のお子様が不利にならない方法です。
どの学校が月齢を考慮しているか、していないかという話は割愛します。
小学校受験の入試日程が異なる場合と同じ場合の月齢考慮の仕方
月齢によって入試日程が異なる学校では、ペーパーや製作の試験内容を変えることができるため、基本的な月齢考慮が行われていると考えてよいでしょう。一方で、入試日程が同じ場合でも合格ラインを変えたり、補欠の場合には学校によって低月齢から補欠を繰り上げる学校もあります。
聞く人によっては、補欠になったときに繰り上げていく順番くらいしか考慮しないの?と思われるかもしれません。慶應義塾幼稚舎、慶應義塾横浜初等部、早稲田実業学校初等部などの学校になるとあまりありませんが、ほとんどの学校では2割3割、学校によっては5割くらいの合格者が辞退して違う学校に移ります。例えば、定員80名の学校で3割が辞退する場合、24名が繰り上がります。その中でもキャンセルが出れば、結果的に30名近くが繰り上がることになります。つまり、80番目に入らなくても、110番目までに入っていれば、低月齢なら合格する可能性があります。
小学校受験では低月齢と高月齢によって差がある
小学校受験は5~6歳児で行われるため、月齢の差はある程度あります。低月齢の保護者から見れば考慮するのが公平と考えますが、逆に4月5月6月の高月齢の保護者から見ると同じ学年なのに考慮することが不公平という見方もできますし、学校側の考え方や対応方法も様々です。
低月齢の小学校受験対策は早めにスタートしましょう
低月齢のお子様を受験させると決めた場合のアドバイスをお伝えします。
何事も「先んずれば人を制す」という言葉があります。高月齢のお子様が2年間準備していて、低月齢のお子様が1年半の準備で、月齢考慮のない学校を受けると低月齢のお子様は不利になります。当研究所の年中時の生徒の月齢割合を見ると、1年間の中で4分の1が1月2月3月の早生まれに相当しますが、会員の割合で見ると、実際は高月齢のお子様が多い傾向にあります。
早く始めたくても我が子の様子を見ていると「まだ少し早い」「今やっても身に付かないんじゃないか」「やって嫌がったらどうしよう」と思い、二の足を踏んで様子を見ようと準備が遅れてしまいがちです。スイミングやバレエ、楽器などの普通の習い事なら遅れて始めても良いと思いますが、小学校受験は年長の秋が期限なので、遅れた分だけ仕上がりも遅れます。
例えば、徒歩10分の距離にある駅に向かって歩き出すとき、3分遅れて出てしまったお子様は追いつくために走るか、早歩きでもしない限り、追いつくことができません。低月齢のお子様に走って追い越すことを求めるよりも、ゆっくりで良いので先に駅に向かって歩き出した方が良いです。歩き出すというのは塾に行き始めるということだけを意味していません。受験の準備は塾に通う以外に、ご家庭で時間を決めて5分10分15分の短時間でも良いので、絵を描いたり、粘土をしたり、折り紙を折ったり、製作的なものであったり、トランプや塗り絵をやってみましょう。
また、市販の問題集がたくさんあるので、年齢相応の問題集をやって、その中で楽しそうなものを取り組んでみましょう。右と左の絵の違いを見るような間違い探しであったり、中には迷路が好きなお子様もいます。その楽しそうなもの、やりたそうなものから、家庭での取り組みを始めましょう。興味がありそうなところから広げていくことがポイントです。
幼児学習は遊びの延長で小学校受験対策をするのが基本
もう一つのアドバイスは、できないことを「低月齢だから」と言う理由にしてしまうと、簡単に諦めて努力が足りなくなる傾向があります。しかし、高月齢のお子様でも切ったり貼ったり折ったりする作業が遅いこともあります。ペーパー問題を中々理解してくれないこともあります。
高月齢の保護者は「高月齢だからできないはずがない」「他のことができるのにこれだけできない、なんていうことはあるはずない」と思っていても、努力を続ければ結果的にできるようになることが多いです。低月齢の場合は「まだ早いのかな」「まだちょっと難しいかな」「無理かな」と思って、やればできることを早めに諦めてしまう傾向があります。諦めないようにすることが大事です。
幼児の学習は基本的に遊びの延長です。先ほど例に挙げたペーパーは雑誌の裏にあるようなレベルで、間違い探しは勉強や学習と謳っているだけであって、内容的には楽しいものも沢山あります。つまり、幼児の学習は遊びの延長で、遊びはできるかできないかではなく、楽しめたか、楽しめなかったかの差です。