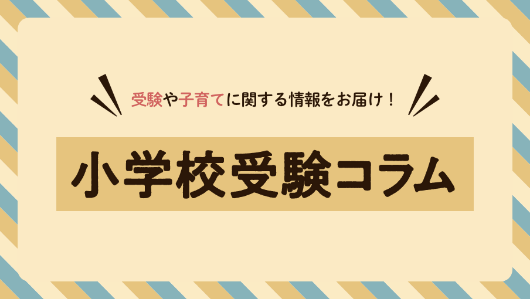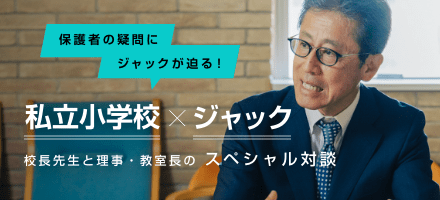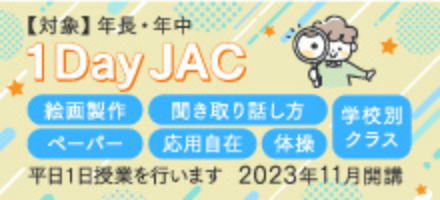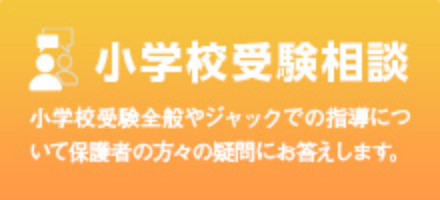子どもが勉強や遊びに夢中になるのは、「楽しい」と感じたとき。では、どうすればその気持ちを引き出せるのでしょうか?カギは「仕掛け」と「演技力」にあります。本記事では、ミラーニューロンの鏡の法則を活かし、親のちょっとした工夫で子どものやる気を引き出す方法を紹介します。トム・ソーヤのように、「やらせる」のではなく、「やりたくなる」環境づくりを一緒に考えてみませんか?
目次
ミラーニューロンの鏡の法則から小学校受験対策の家庭学習法を学ぶ

なぜ食事は美味しいと言って食べるのでしょうか。それは家族みんなで美味しく食べているからです。
なぜもらい泣きをするのでしょうか。それは脳に「ミラーニューロン」と呼ばれる共感の元となる神経細胞があるからです。この神経細胞の働きによって、他人の行為を観察しているときに脳内で同じ体験をすることができます。
つまり、子供にペーパーをやらせて保護者が難しそうな顔をしながら「お勉強、楽しいでしょ?」と言っても、子供は楽しい気持ちにはなれないのです。一方で、お母様やお父様が笑顔で「よく考えて、よく見て綺麗に塗りなさい。丁寧に折りなさい。そして、もっと早く手を動かして」とニコニコしながら言えば、子供も取り組みたい気持ちになります。ただ、それができるのは30分が限界かもしれません。
もしもお子様が勉強をやりたがらなかったり、折り紙を折りたくない、絵を描きたくないのであれば、お母様やお父様が楽しそうに折り紙を折ったり、絵を描いたり、場合によってはペーパーも「結構これ難しいね」と言いながら取り組んでみるのが良いでしょう。そうすると、その相手の動きを見て真似をする脳の仕組み、つまりミラーニューロンの鏡の法則が活用されて「楽しいんだな」「やってみたいな」という気持ちになっていきます。
小学校受験では保護者の「演技力」と「仕掛け」が子どもの学習意欲を上げる
保護者が楽しそうに絵本を読んだり、パズルや折り紙、本、トランプなどをしていると、子供も必ずやりたくなります。子育てで必要なのは、ちょっとした仕掛けと演技力です。保護者が楽しそうに取り組んでも子供がやりたいと言わなければ、何かが足りない可能性があります。保護者自身が楽しそうにしていないのか、例えば塗り絵の場合、あまりにも綺麗に塗りすぎてしまうと、子供が「こんなに上手に塗れそうにないな。もっと綺麗に塗りなさい。と言われるかもしれない」と思って引いてしまうこともあります。
折り紙でも同じです。難しいものを折りすぎたり、綺麗に折りすぎたりすると、お子様がやりたがらなくなる可能性もあります。
ほかにも、パズルなど「難しいな」と言いながら取り組んでみるのも良いかと思います。もちろん「楽しいな」と言うのも良いですが、「ちょっと難しいな」と言いながら最後まで完成させず、何ピースか残した状態で置いておくのも効果的です。そうするとお子様が「んーこれこうじゃない?」「お母さんできたよ!」と言って見せてくるかもしれないので、お母さんが「えっ、あれできたの?すごいわね」と言ってあげましょう。お子様は得意気になったり、もっとパズルをやってみようという気持ちになるかもしれません。
小学校受験に必要な演技力と仕掛けのヒント
「トム・ソーヤのペンキ塗り」に学ぶ
「トム・ソーヤのペンキ塗り」という話には、やりたがらない子を誘うヒントが隠されています。
話の内容は次の通りです。
友達が「ペンキ塗りって嫌じゃない?」と尋ねると、
トムが「とんでもない!こんな楽しいこと他にはないよ。邪魔しないでくれ」と言って仕事に夢中になります。
すると友達は「え?楽しいの?」
トム「君はペンキ塗りの楽しさ知らないの?」
友達「そんなに楽しいなら僕にもやらせてよ」
トム「とんでもない。こんな楽しいこと、君には譲れないよ」
友達「そんなこと言わずに少しだけやらせてよ」
トム「ダメダメ!これは僕にしかできないことなんだから」
友達「じゃあビー玉あげるから」
トム「え?ビー玉何個持ってるの?」
友達「10個」
トム「そうか。んー仕方がない。じゃあ1mだけ塗っていいよ」
友達「ありがとう」
友達が一生懸命塗り始めます。少し調子が出てきたところで
また「1mやったからもう終わりだよ、もうここまでにして」とトムが言います。
そして友達は「楽しくなってきたから、もうちょっとやらせてよ」
トム「ダメダメ。こんな楽しいこと、これ以上はやらせられないよ」
友達「じゃあ、ビー玉もう10個あげるから、もうちょっとやらせてよ」
トム「ビー玉?今あるの?」
友達「今ないから後で」
トム「後でじゃダメ、今じゃないとダメ。」
友達「じゃあ今すぐ取ってくるから待っててね」
トム「すぐ戻ってくるんだよ。そうでないと終わっちゃうよ。」
その後、トムは壁の前でサボっているのです。また別の友達がそこを通りかかると、トムはすぐに楽しそうにペンキ塗りを再開します。
そして、そうしながら、また別の友達が「何してるんだい」と話しかけられても一生懸命に塗って気付かないふりをするのです。
こうしてトムは同じように、次々と通りかかった友達と宝物を交換しながら、ペンキ塗りの仕事を終わらせます。
最終的には長い長い壁を全て塗り終えるだけでなく、宝物と交換することができましたというお話です。
もしトムが嫌々ペンキ塗りをしていたら誰も「やらせて」とは言わなかったでしょうし、逆に「手伝って」と誘えば「なんでそんなことしなきゃいけないの」と見向きもされなかったでしょう。
小学校受験は親が役者になることで子どものやる気度合は変わる
この話には人がやりたくなる心理と演技力が表現されています。お子様の性格によって時間差はあっても、親が役者になり楽しそうに取り組むことで必ずお子様もやりたくなるはずです。